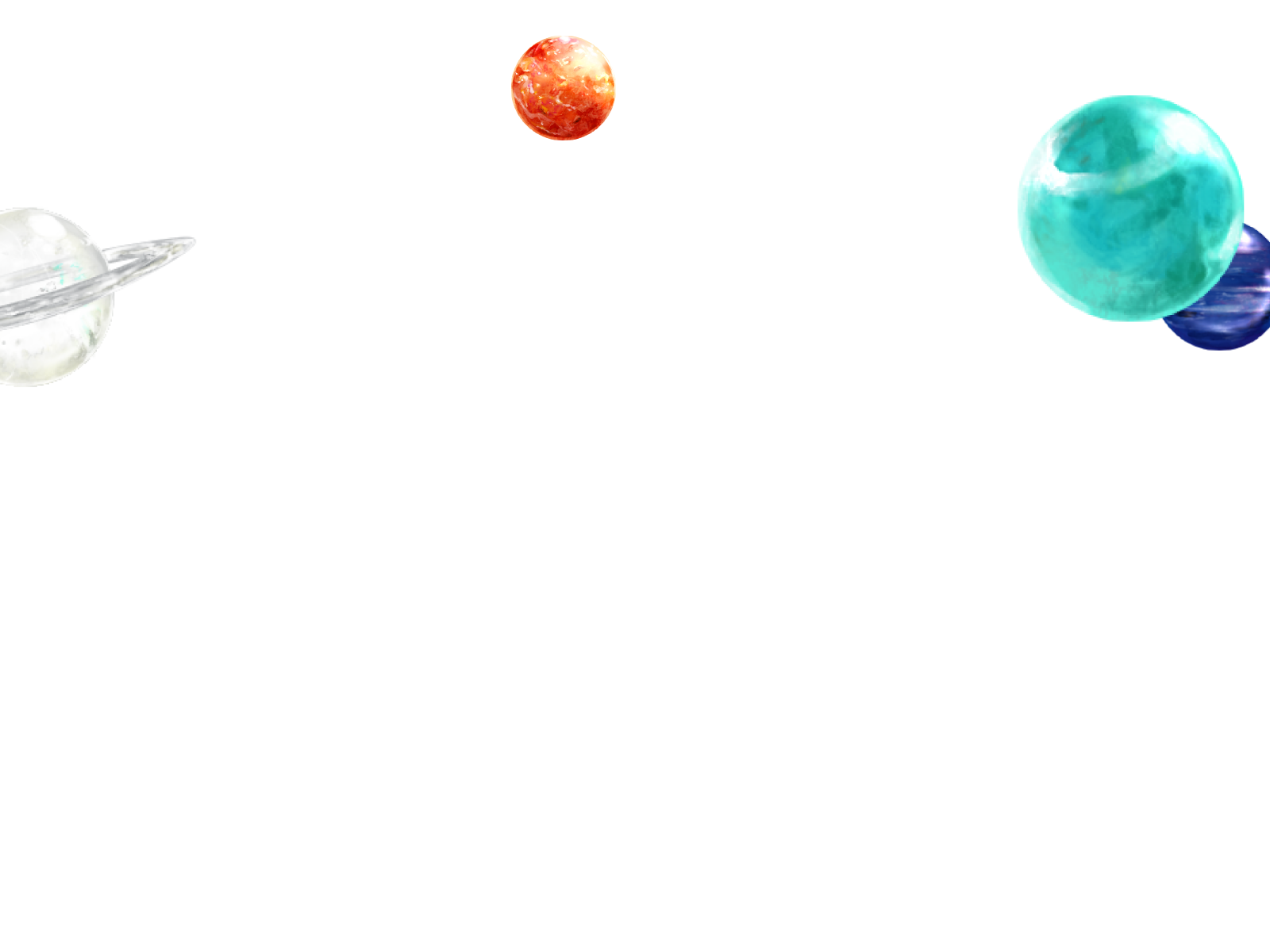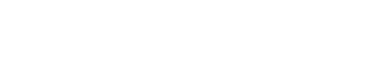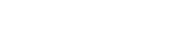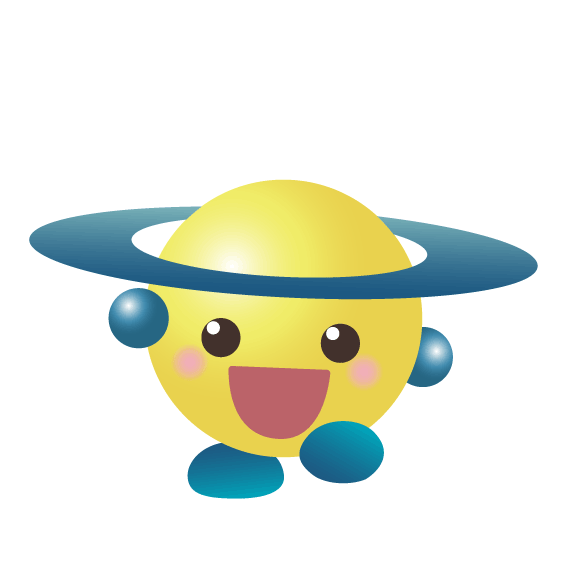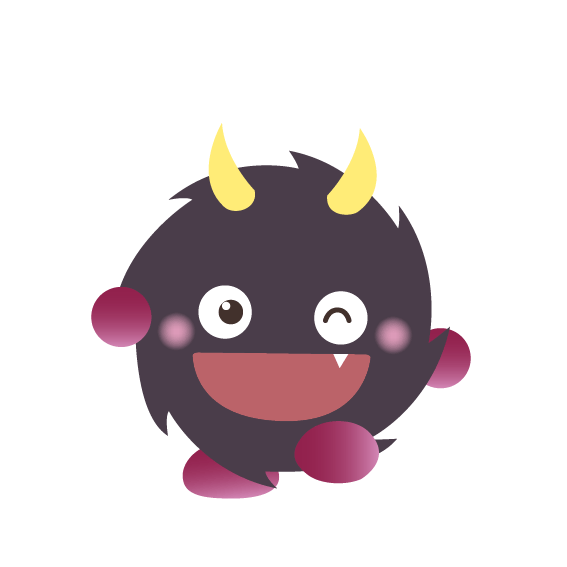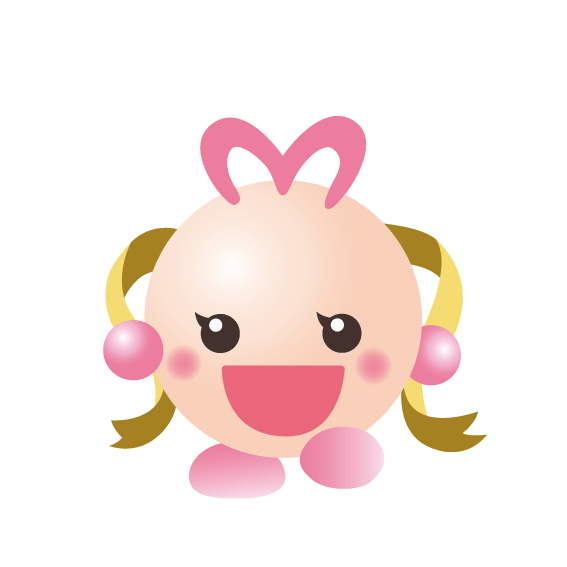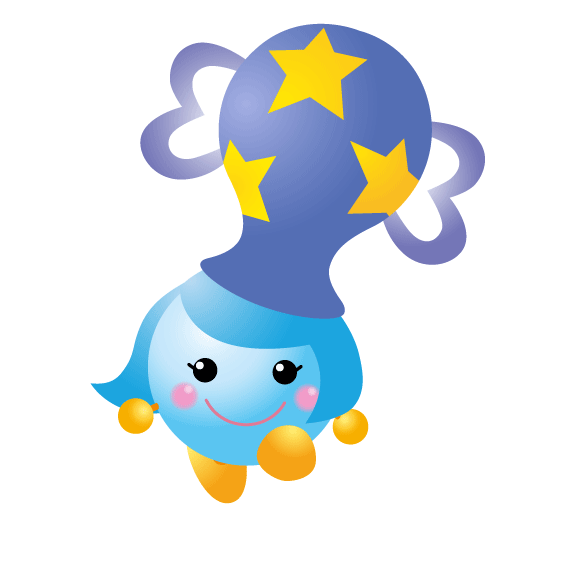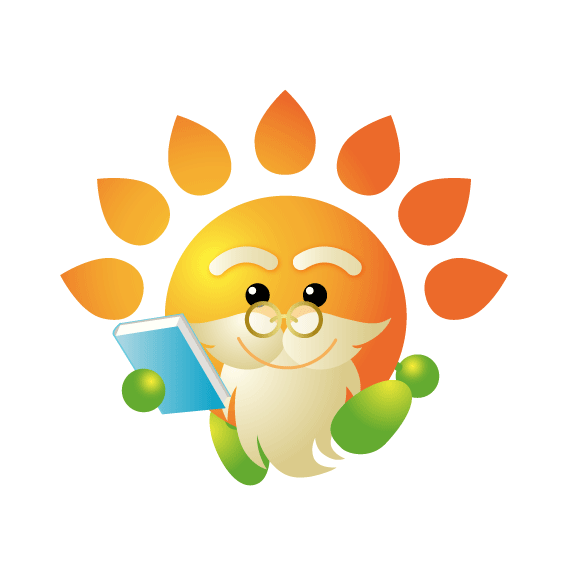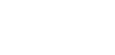コラム「泣きながら草の根を噛む蟻」
コラム「泣きながら草の根を噛む蟻」
 良樹細根
良樹細根
2024年10月17日
「根深ければ、葉繫し」と申します
根が細かく深く張っている樹の葉は、見事に生い茂っています
同様に樹は、広く、深く、細かく根を張っていなければ
大樹に育ちません
教育も事業も同じ
すぐに役に立つことばかりしていますと、根がおろそかになります
何事も、最初に手をつけるべきはいつも根で、葉は後
2024年9月7日
国民教育学者 森信三先生が次のような意味の言葉を遺しています
「どんな素晴らしい教えでも、相手が心を開かなければ伝わらない
それは、伏せたコップの上から水を注いでいるのと同じである
まずコップを上に向けさせることが大切だ」
聞く耳を持たない人にどんなに良い話をしても、反発を買うだけです
教育の原点は、まず相手の心を開かせることです
2024年7月9日
「挨拶に始まり挨拶に終わる」と言う言葉があるように
人間関係において挨拶はとても大切なものです
それは相手との関係を良くしたいという気持ちの表れであり
社会生活のさまざまな場面で挨拶は行われています
挨拶という言葉は、もともと禅語の「一挨一拶(いちあい いちさつ)」
から派生したものと言われています
「挨」も「拶」も同じく「互いに心を開いて接すること
ひいては互いに認め信じあう」ことを意味しています
日本ではお辞儀など頭を下げる挨拶はありますが
両手を合わせて挨拶をしたり、握手をしたりする国もあります
このように国によって作法は異なりますが
「挨拶を交わす」ことは世界中で共通して行われていることです
人と人との関係を円滑にする「挨拶」には多くの人の心を
明るく豊かにする力があるのかもしれませんね
2024年5月22日
保育士でもあった中川ひろたかさんの絵本
「おおきくなるっていうことは」
自分は本当に成長しているの?
大人だって一緒に考えたくなる一大テーマなのかもしれません。
おおきくなるっていうことは
洋服がちいさくなるっていうこと
新しい歯がはえてくること
水に顔をながくつけられるってこと
あんまり泣かないってこと
子どもたちの毎日は「おおきくなる」よろこびであふれています
身体の成長はもちろん、面白いことをたくさん見つけられる思考力や洞察力
この高さからジャンプしても大丈夫かな?
という判断力
泣くのをぐっと我慢する忍耐力
自分のことだけじゃなく、相手を思いやる心の成長も
あらゆるところが少しずつ育ち、変わっている
振り返ると、いつの間にか昔の子どもとは違う姿に気付き、ぎゅっと抱きしめたくなります
「おおきくなったね!」と
2024年1月5日
ある本に書いてあった内容です。
心と身体の繋がりを研究する運動心理学によれば
自分自身で創り上げたセルフイメージ以上のことが実現する可能性は
極めて低いことが証明されています。
セルフイメージとは、自分が抱いている自己イメージです。
大リーグで活躍する大谷翔平選手、プロサッカー選手として活躍した本田圭佑さんが
小さい頃から大きな目標を持ち、具体的に未来の姿をイメージして努力した結果
今に至っていることは有名です。
高い目標に向かって努力することは、頂上を目指して進んでいく山登りに似ています。
まっすぐな道を選択し、厳しい急勾配を一気に登っていく人もいれば
緩やかな道を選び、ゆっくりと自分のペースで登っていく人もいるでしょう。
それぞれの歩みは違っても、それでよいのです。
大切なことは実現したい目標に向かって、昨日よりも今日、今日よりも明日へと
コツコツと自分の決めたことを達成していくことです。
その積み重ねこそが、成長となり自信へと繋がります。
2023年11月28日
光陰矢の如しという諺があります
「月日の経つのは飛んでいく矢のように非常にはやいので
無駄に過ごしてはいけない」という意味です
一生という与えられた時間の中で、意義のある時間を過ごしていくことができれば
それは時間に「いのち」を吹き込む貴重な積み重ねとなるに違いありません
「あの時は、人生の中で一番努力したな」
「あの時は、よく夜中まで勉強していたな」
「全国大会を目指して、毎日部活動を頑張っていたな」
というように
青春時代の充実感に満ちた時間は「光陰矢の如し」の中に
あっても、生きる意味と価値を見出すものとなります
そしてその時間は、かけがえのない宝物となって
生涯記憶に残り続けることでしょう
2023年6月29日
ある本にこんな内容が書かれていた。
「笑い」について認知症や鬱病に好結果を生むなど、その効果がマスコミなどにも
取り上げられている。
しかし、笑って一生を過ごせるならいいが、人生そう甘くない。
嫌なこと、辛いことがたくさんある。
新聞にこんな記事を見つけた。日本医科大学付属病院リウマチ科の医師が、ある日落語家を招いて患者に落語を聞かせた。
すると多くの患者が膝の痛みが楽になったという。
また、あるテレビ番組で脳神経外科医の先生が「笑い」は癌や糖尿病、リウマチなどの難病にも効果があると言っていた。
つまり「笑い」は呼吸を深くし、心と身体を緩ませ、安心感や喜びを心の底から湧き上がらせる。そして心理的なエネルギーのロスが少なくなった分、バイタリティーが増える。
この葛藤がなく生命力に満ちた心身の状態を、人は幸福の状態だという。
「笑い」はただ表情筋を緩めるだけ。反対に笑わなければ、笑えなくなる。使わない筋肉はどんどん退化し、無表情になっていくらしい。
日々の生活の中で、ほんのちょっと口角を上げる意識を習慣づけていきたいと思う。
2022年11月11日
カニ
私はカニが大好きです。年末になるとカニの新聞広告をよく目にします。複数の会社が広告を出しており、魅力的な宣伝文句にあふれています。『身の詰まりが他とは違います』、『カニを扱って○○年のバイヤーが選ぶ』、『リピート率80%』、『〇月△日までのご注文で早割』、『お客様満足度95%』等々・・・決められません。「A社もいいけど、B社も良いぞ~。決して安くない買い物だし、慎重に考えよう」と思っている間に早割の時期を過ぎてしまいます。そして、考えるのに疲れ果てて、「今年は止めておいて、来年はすぐに決めよう」と諦める・・・これが毎年です。まだ11月。今年こそ美味しいカニを買うぞ~。
2022年10月20日
ハイハイは 「リズム運動」の基礎づくり
「立っち」は 「根気」の基礎づくり
人見知りは グループや仲間意識の基礎づくり
動作のマネっこは 「ルールを守る」基礎づくり
指差しは 「選択する能力」の基礎づくり
初めての言葉は 「ひらめき」の基礎づくり
ちょうだいは 「分かち合い」の基礎づくり
子どもにとっては様々な発達の積み重ねがあって
その一つがズレると思うように身体が動かない
一つひとつの「できた」が 大きい「できた」につながっていく
2022年7月15日
窮屈な世の中にされてしまった。
何によって?はとりあえず置いておいて、
窮屈な世の中になってしまった。
こんな状況に輪をかけるように我々日本人は
【事態を早く解決しないといけない、という強迫観念】
にとらわれがちである。
体調が悪くて仕事を休んだ時には「早く回復して出勤しないと」。
誰かと話していて、間ができると「何か話さないと」。
うつ気味の人は「早く元気にならないと」など、など。
まるでそう強く迫られているかのように自分の事を観てしまう、
誰に「そう」言われたわけでもなく。
このような「本当は存在しない暗黙のルール」に、我々は悩まされてしまう。
これが悪循環してより悪化させてしまっている事がこの世界にはたくさんありそうだ。
仕事を休んだなら、この際、見ようと思ってまだ見ていなかった映画を見ればいい
話していて間が生まれたなら、その間も大切な会話の一部分であると見方を変えればいい
うつ気味のまま、ゆっくりと流れる時間を、ゆっくりと流れる時間のまま身を委ねればいい
言うは易く行うは難し、
されど1人1人が少しずつその意識を持ち、
隣の人と、今までより少しだけのんびりと関わるようにしていくことが、
この閉塞感を和らげる第一歩になるのではないだろうか。